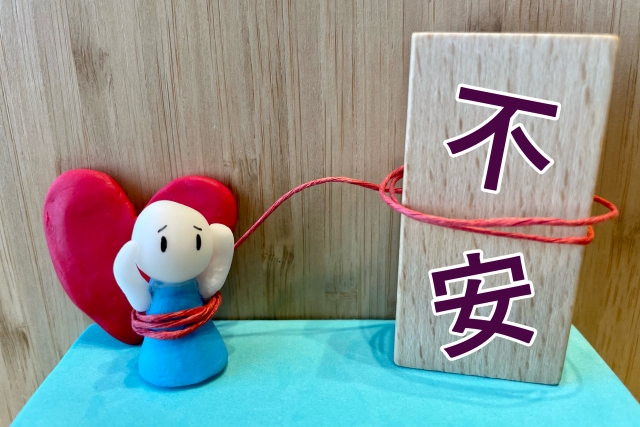私は『幸せになるために確実に足を引っ張てるなぁ~』と思う感情があります。
それは何を隠そう『不安』です。
この『不安』という気持ちが私たちを委縮させ、幸せになるための道を妨害しているなぁ~!って思うんです。
この『不安』ってやつを何とかやっつけてやりさえすれば、幸せをもっともっと身近に感じられるような気がします!
では、相手(不安)をやっつけたいと思うのですが、やっつけるためには、まず相手のことをよく知る必要があります。
不安という感情が人間に備わった理由
そもそも不安って私たちを委縮させ、幸せになるための道を妨害しているだけならそんな感情、人間に備わらなくてもよかったんじゃないか?って疑問が湧いてきます。
そう!
不安というのは人間にとって必要な感情だったのです。そうでなければ、やはり備わることはなかったのかもしれません。
ではどんな時に必要な感情だったのでしょうか?
- 危険回避: 不安は、潜在的な危険や脅威に対する警告システムとして機能します。これにより、危険を避けるための適切な行動を取ることができます。例えば、原始的な環境では、肉食動物や自然災害から逃れるために不安が役立ちました。
- 問題解決: 不安は、将来の問題や課題に対して準備を促すことがあります。不安を感じることで、計画を立てたり、リスクを評価したりする動機づけとなります。
- 社会的結束: 不安は、社会的な絆を強める役割も果たします。グループ内で危険を共有し、それに対処するために協力することで、生存率が向上しました。
- 適応反応: 不安は、急な環境の変化に対する適応を促進する要素でもあります。不安を感じることで、新しい環境や状況に対して迅速に対応することができます。
このように、不安は単なるネガティブな感情ではなく、生存や適応のために重要な役割を果たしてきたのです。もちろん、現代社会では過剰な不安が問題となることがありますが、適度な不安は依然として重要です。
そうです、不安な気持ちがあるからこそ人間はピンチを察知することができ、事前に回避することができたのですね。
では現代に置き換えて、もう少しわかりやすく、どんな時に不安を感じるのか見てみましょう。
不安になる原因
- ストレス: 仕事や学校、人間関係などの日常生活のストレスが不安感を引き起こすことがあります。
- 不確実性: 将来の出来事や結果が不確定な場合、人は不安を感じることがあります。
- 過去のトラウマ: 過去の辛い経験やトラウマが、不安を誘発することがあります。
- 健康問題: 身体的または精神的な健康問題が、不安の原因になることがあります。
- 環境の変化: 引っ越し、転職、結婚などの生活の大きな変化が、不安を引き起こすことがあります。
また、遺伝的要因や脳の化学的な不均衡も関与していることがあるため、不安の原因は複雑で個別的です。何が原因で不安を感じるかを理解することは、不安を管理するための重要なステップです。
不安の主な構成要素
- 心理的要素: 考え方や感じ方が不安に影響を与えます。例えば、「失敗するのではないか」というネガティブな思考が不安を引き起こすことがあります。
- 身体的要素: 心拍数の増加や発汗など、身体的な反応が伴うことが多いです。これらは、身体が「危険」に備えている兆候です。
- 行動的要素: 不安によって、特定の行動を避けたり、過度に準備したりすることがあります。これは、不安を和らげるための戦略です。
不安は時には有益ですが、過度な不安やコントロールできない不安は、日常生活に支障をきたすことがあります。
不安は時には有益であったり、必要であることはわかりました。
しかし、大きすぎる不安は日常生活に支障をきたしたり、前進することができなくなってしまったりして、私たちから幸せを遠ざけてしまうことがあるということがわかりました。
不安を大きくしすぎないための方法
では、やはり不安を大きくしすぎないことが必要言うことがわかりましたので、不安を大きくしすぎない方法を学んでいきましょう!
まず、皆様に知ってもらいたいことがあります。
それは…
あなたの思い描く不安の約9割は実際に起きない
という事実です。
正確には9割という数字は具体的な統計データに基づくものではないようですが、心理学者は私たちが抱える多くの不安や恐れが、実際には過剰なものであることを示しているようです。
例えば、研究によれば、不安を感じる出来事のほとんどは、実際には起こらないか、起こったとしてもその影響は私たちが想像するほど大きくないことが多いと言われているそうです。
ですから、先ずは「心配しすぎるな!」っていうことなんです。
次に不安を大きくしすぎないために行うとよいことを上げたいと思います。
不安を感じたとき、それを小さく抑えるための方法
1.現実的な考え方を取り入れる
不安を感じたとき、その原因や結果を現実的に評価しましょう。実際に起こりうることと、自分の想像に過ぎない部分を区別することが重要です。
2. 呼吸法やリラクゼーション
深呼吸や瞑想、ヨガなどのリラクゼーション技法を取り入れると、心を落ち着ける効果があります。これによって、身体的なストレス反応を抑えることができます。
3. 運動をする
運動はストレスを軽減する効果があります。特に有酸素運動は、エンドルフィン(幸福ホルモン)を増やし、不安を和らげる助けになります。
4. ポジティブな思考を育てる
ポジティブなことに焦点を当てる練習をしましょう。感謝の気持ちを持ったり、毎日の良い出来事を振り返ることが役立ちます。
5. サポートを求める
信頼できる友人や家族、専門家に話をすることで、不安が軽減されることがあります。外部の視点を得ることで、より冷静に考えられるようになります。
6. 規則正しい生活を送る
バランスの取れた食事、十分な睡眠、規則的な日常生活を心がけることで、心身の健康を保つことができます。
どの方法があなたにとって最適かは、試してみることで見つけられます。どれか一つでも日常に取り入れることで、不安を感じる頻度や強さが減るかもしれません。
このように不安をなるべく小さいものに抑える方法はありますが、私の見解で一番良いと思っていることは
心に隙間を作らないということです。
つまりは、好きなことややりたいことをたくさんやって常に脳が忙しい状態を作るということです。
これが、幸せな人は切替がうまいといわれる所以ではないかと私は思います。
そうなんです。
やっぱり、幸せと感じている人はやりたいことがたくさんあり、生き生きとしているように感じませんか?
なんか、毎日あれやこれやとやって忙しそうにしていませんか?
もちろんそれを楽しくやっている、そんな風に感じる人はやはり幸せそうだし、本人も幸せを感じているのではないでしょうか?
忙しいですからね、前にあった何か辛いことや嫌だったことなどを考えている暇がないんです。
だから、不安を感じる時間がそもそもない。のだと私は思います。
せっかく生きているのですから、やっぱり人生楽しまなければいけません^^
幸せにならないといけないのですから…
まとめ
今回ご紹介したように不安への研究や不安を解消するための方法などいくつかの研究や考え方があります。
そういったことをまとめると次のようなところになります。
1. 心理学的研究: 多くの研究が示すところでは、私たちが心配することの大部分は実際には起こらないか、思っていたほど深刻ではないことが多いです。
2. 認知行動療法 (CBT): CBTの一環として、不安を感じる状況や思考パターンを評価し、それが現実的かどうかを検証することがあります。この過程で、多くの心配事が根拠のないものであることが明らかになります。
3. マインドフルネスとリラクゼーションテクニック: これらのテクニックは、現在に集中することで将来の不確定な事柄に対する過度な不安を減少させることができます。
このようなアプローチを通じて、私たちの心配事の多くが実際には起こらないという認識を持つことができ、不安の渦に巻き込まれないようになるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。