人は、誰かにつけた“ラベル”を通して相手を見てしまう。
そして、そのラベルが一度貼られると、なかなか外せなくなる。
1973年、心理学者デイヴィッド・ロゼンハン(David L. Rosenhan)は、
この「ラベリング効果(レッテル効果)」を明らかにする実験を行いました。
その結果、人は他人を「その人自身」ではなく、「与えられたラベル」で見てしまうという
衝撃的な心理のメカニズムが明らかになったのです。
🧪実験概要(When・Who・How)
-
実施年:1973年
-
研究者:デイヴィッド・ロゼンハン(米・スタンフォード大学心理学者)
-
発表論文: “On being sane in insane places(正気でいながら狂気の場所にいるということ)”
参考資料【精神病のフリして入院】アメリカ全土を震撼させた「ローゼンハン実験」とは? -
目的: 精神科医の診断が「ラベル(先入観)」にどれほど影響されるかを検証すること
🧍♀️実験方法
ロゼンハンは、精神的に健康な8人の協力者を集め、
それぞれが「幻聴が聞こえる」と偽って全米12の精神病院を受診させました。
その後、入院が決まると幻聴の訴えをやめ、
普通に生活しながら職員たちの対応を観察します。
📊結果
驚くべきことに、8人全員が精神疾患ありと診断され、入院を許可されました。
(診断名はほとんどが統合失調症)
さらに、入院後に「もう幻聴はしません」と伝えても、
医師たちは「病気が一時的に落ち着いているだけ」と解釈。
健康な言動さえも“病気の証拠”として見なされてしまいました。
平均入院日数は19日間、最長で52日間にも及びました。
最終的に全員が「寛解(回復)」という形で退院しましたが、
診断書には「誤診でした」とは書かれませんでした。
🧩ロゼンハンの考察(What it means)
ロゼンハンはこの結果から、次のように指摘しています。
「一度“狂気”というラベルが貼られると、
その人のすべての行動は“狂気の証拠”として解釈されてしまう。」
つまり、人は他人をラベルを通して解釈してしまう傾向があるのです。
これを心理学では「ラベリング効果(Labeling Effect)」と呼びます。
🧭社会的な示唆
この実験は、単に医療現場だけでなく、社会全体に衝撃を与えました。
「一度“問題児”や“できない人”と見なされると、
その印象が覆りにくい」という構造が、学校・職場・家庭にも当てはまるとされたのです。
-
「いい子」ラベル:常に期待通りに振る舞おうとするプレッシャー
-
「悪い子」ラベル:何をしても否定的に見られ、信頼を取り戻せない苦しさ
つまり、どんなラベルであっても、人の“自由な成長”を奪う危険性がある。
これが、ロゼンハンが社会に投げかけたメッセージでした。
🪞まとめ:ラベルの怖さと人間関係への教訓
ラベルは、便利な“思考の省略”である一方で、
人を固定化してしまう“無意識の罠”でもあります。
人は変わる存在です。
にもかかわらず、私たちは「過去の印象」や「肩書き」で人を判断しがち。
ロゼンハン実験が伝えたのは、
「見えているのは、あなたのラベル越しの相手では?」という問いかけなのです。
🧠ポイント
人は一度つけたラベルを基準に、相手のすべてを判断してしまう。
「いい子」「悪い子」「できる人」「ダメな人」——
どんな言葉も、見方を固定してしまう危険をもつ。
ラベルを外して“その人自身”を見よう。
-
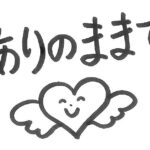
-
「いい子」「悪い子」ラベルとは? 〜“評価”ではなく“存在”を認める関わり〜
続きを見る
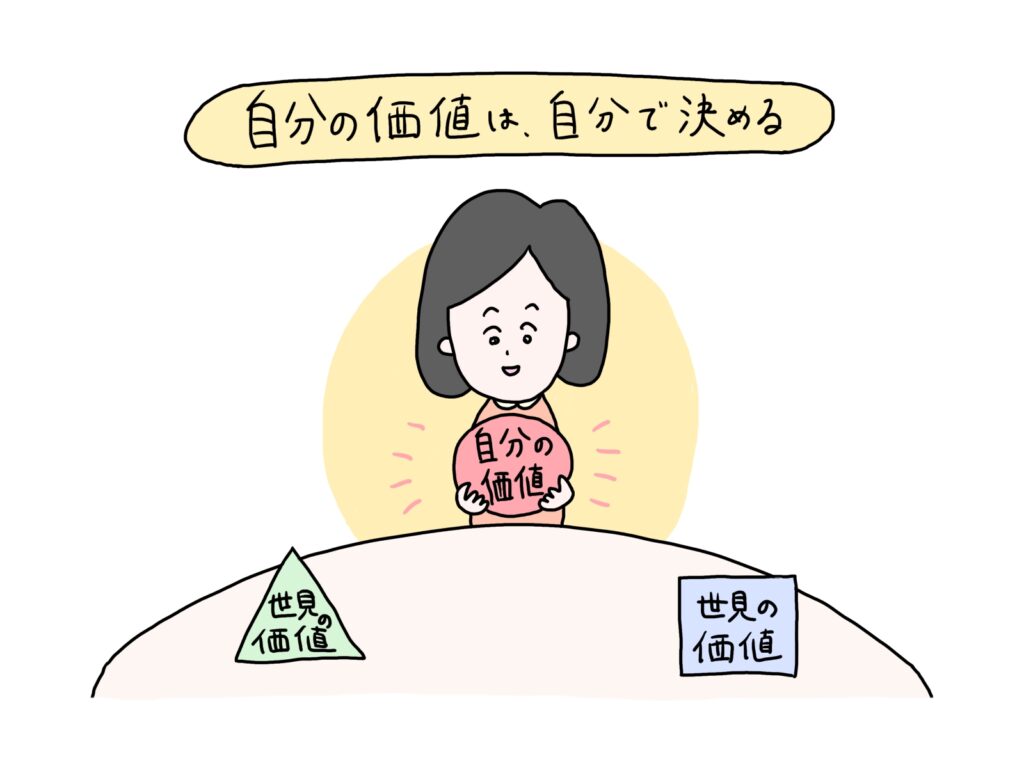
🌱 ラベルは“呪い”にも、“魔法”にもなる
ロゼンハン実験は、「人は先入観で他人を見てしまう」という怖さを示しました。
でも、それは同時に、**「見方を変えれば、人を変えることもできる」**という希望でもあります。
たとえば、「この子は優しい」「あなたならできる」といった言葉も、
ラベルの一種です。
しかしそれが**“信じるラベル”や“期待のラベル”**であれば、
人の成長を引き出す力に変わります。
大切なのは、ラベルを貼ること自体ではなく、
どんなラベルを貼るか、そして貼りっぱなしにしないこと。
見方を変えれば、ラベルは人を縛る“呪い”ではなく、
可能性を広げる“魔法”になるのです。
🌿ラベルを外すことも、貼りかえることもできる。
それをできるのは、いつだって“人のまなざし”なんです。
